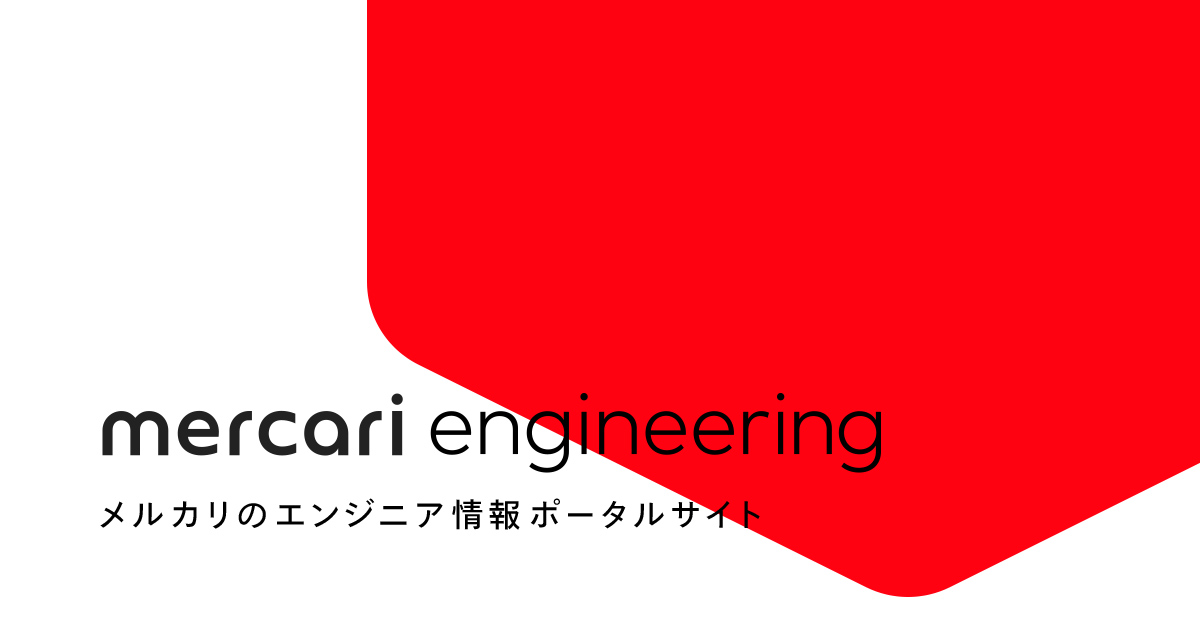データ分析チーム立ち上げ完全ガイド(後編):国内外のデータ分析チーム成功事例と失敗からの教訓
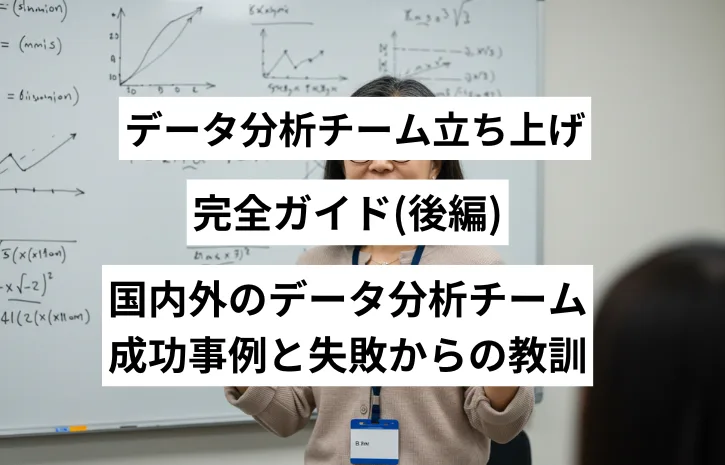
こんにちは!サステックスのAIエンジニア、須藤です。
この記事は前編、中編、後編の3つから成るデータ分析チーム立ち上げ完全ガイドの記事になります。
後編を持って完結ですが、前編、中編も合わせて読んでいただけると、よりデータ分析チームの立ち上げに関して理解が深まるかと思います!
前編ではデータ分析立ち上げに関するチームの目的設定、役割、組織設計に関して解説をしました。
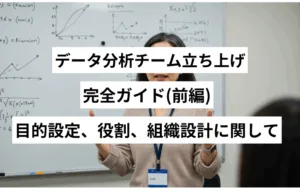
中編では、分析チームの具体的な進め方に関するロードマップに関して記載しました。
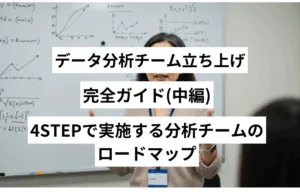
本記事では国内外のデータ分析チームの立ち上げ事例を紹介していきながら、成功した要因、失敗した要因に関してご紹介していきたいと思います。
前編、中編ではかなり理屈っぽい話をしていましたが、実際の立ち上げ事例から学べる事は多く、データ分析チーム立ち上げの成功確率を高める上で非常に有益です。
国内外の先進企業の取り組みや、残念ながら失敗に終わったケースから得られる教訓は貴重な指針となるはずです。
データ分析立ち上げにおける国内企業の事例
日本の企業においても、データ分析チームを立ち上げて成果を上げている事例が数多く報告されています。
メルカリの事例
メルカリはデータ分析、データ基盤やAI活用においての取り組みを多く発信している国内における先端的な企業の一つです。特にデータ関連には多くの施策を行っているので、本記事にて紹介していきます。
メルカリの公式のエンジニアリングブログは技術者にとって有用な記事が多いので、特にデータ分析やAI活用を進めている方にもおすすめです。
チーム体制とミッション: BI
少し前の記事ですが、メルカリBIチームのミッションは「意思決定力のMAX化」。
分析「だけ」が目的ではなく、プロダクトや経営判断を伴走して導くことをミッションとして、部署横断的に配置され、コミュニケーションと意思決定までのスピードを最大化しているようです。

データの民主化
データの民主化、という概念があります。「データの民主化」とは、誰もがデータにアクセスして理解し、活用できる状態にすることを意味します。たとえ、データ分析の専門家を雇えたとしても、マーケティング、営業、製造などの非専門部門のメンバーがデータやAIの活用が出来ていないと長期的な売上向上には繋がりづらいです。
メルカリでは、全従業員のデータ分析への心理的ハードルを下げるための「ゆるふわBI」という独自の取り組みがあり、様々な部署から約180名が参加しています。Slack上でチャンネルを開設して、「ゆるく何でも聞いて」というスタンスで非専門家の人たちの理解を深めているようです。
データ分析基盤の構築に関して
メルカリのデータ基盤は国内でも先端的な技術を採用していて、技術者観点でも経営者観点でも面白い取り組みが多いです。また失敗した事例などの紹介もしており、データ分析チーム立ち上げ時に、参考になる内容も多く含まれています。フェーズや業種、社内体制によっても最適解が常に変化してくる分野なので、このようにPoC(仮説検証)を繰り返していけるチームはやはり継続的に成果を出せるチームの大きな要因と言えます。
例えば、複数の機械学習チームがあるような会社では「機械学習基盤の共通化」というのは誰もが考えた事がある内容だと思いますが、こちらの記事ではメルカリ内の共通基盤構築の際の立ち上げ、失敗、振り返りなどが記載されています。

星野リゾートの事例
星野リゾートは日本を代表する総合リゾート運営企業です。星野リゾートでは、Zoho AnalayticsとZoho CRMと呼ばれるCRMを導入した事によって、PDCAを早く実行出来るようなデータ基盤を構築しています。
| 導入前 | 導入後 | 成果・インパクト |
|---|---|---|
| 拠点別 Excel 手入力 → 2週間かけて手動集計 | データをクラウドに自動集約し、営業・マーケ部門が共通ダッシュボードを共有 | – 広告/営業施策の効果を即時確認 – PDCA サイクルを「2週間→リアルタイム」に短縮 |
| 「経験と勘」で原因分析 | 来館予約〜成約までの全プロセスを指標化 | – 予約キャンセル率を 50%削減 |
| 部門ごとにデータが分散 | 部門横断で KPI を可視化し、自分でレポートを作れる環境 | – 担当者が得意セグメントに集中配置→成約率改善 |
| 市場停滞時に慎重姿勢 | データで「リゾート婚ニーズ増」を即検知 | – コロナ禍でも攻めの広告投資を判断し、需要を先取り |
この事例から学べる事としては、
- CRM と BI の連携で「一次情報」を一元化
分散データを集約し、“見える化”までワンストップで回る仕組みを先に作る。 - 部門をまたぐ共通ダッシュボードと分析
上流(広告・営業戦略)と現場(会場担当)が同じ数字で会話できるため、施策と結果のループが速い。 - リアルタイム指標でボトルネックを即特定
例:予約〜来館のリードタイムが一定日数を超えるとキャンセル率が跳ね上がる──数値で根拠を示し、すぐに施策を打てる。 - データに基づく「常識破り」の決断
市場の逆風下でも、需要シグナルが見えれば広告投資を増やすなど、“勘”ではなくファクトドリブンで攻めに転じる。
特に、ダッシュボードを見るだけで終わらせず、部署間で共通認識を持って意思決定が出来る、という事はまさにデータを活用出来ている成功事例と言えると思います。また、評価指標がキャンセル率、広告のROASといったビジネス的な価値に直結した指標になっっている点も重要です。

SOMPOホールディングスの事例
SOMPOホールディングス株式会社は、日本を代表する保険系持株会社で、国内外の保険事業を主に扱っている会社です。約130年の歴史がありますが、2016年よりデータ利活用を進めており、3つのSTEPで長期的にデータ利活用を進めています。
SOMPOホールディングスが進めていた3STEP
STEP1: 構想・トライアルを進めて、SOMPO Digital Labを発足。Tableauを活用したデータの可視化・分析を進めるとともに、社内のデータ活用プラットフォーム「JOY」の開発・構想化。
STEP2: 基盤強化期では、2019年にJOYの拡張を決定。データ活用文化の定着を目指し、データ活用ニーズ、デー活用促進のための基盤構築を実施。
STEP3:展開・拡大期では、グループ全体のデータ活用を推進し、全社員向けのTableauダッシュボードをリリース。1日1万アクセスなど多くの社員がデータを活用。
| データ活用推進前 | データ活用推進後 | 成果・インパクト |
|---|---|---|
| 部門ごとに散在したデータ、分析は一部の専門部署のみ | 2016 年 Tableau を核にデータ基盤「JOY」開始 → 22 年に全社展開し 1 日約1 万アクセス の共通BIへ | 内製化による費用削減/業務効率化/売上拡大 の3KPIで投資対効果を可視化 |
| 指標が部門ごとにバラバラ、経営と現場で数字が噛み合わない | 24 年度「SJ-R」プロジェクトで 共通の重要指標を定義、経営~現場が同じダッシュボードを見る | リリース初週で 5,000 名が利用、現在は1 日1 万アクセス;課題特定〜打ち手決定が即日化 |
| KPIを厳格に決めすぎて着手が進まない懸念 | STEP1: トライアル(KPI設定なし)→STEP2: 基盤強化→STEP3: ROI算定 の段階的アプローチ | 「小さく始めて成功事例を量産」→後からROIを算出することでスピードと説得力を両立 |
こちらの事例で学べる事は、
- “環境>指標” の優先順位
初期は KPI をあえて置かず、誰でも触れる基盤を最短でリリース。
小さな成功体験を積みながら後から ROI 計測を追加する。 - UX ファーストのダッシュボード設計
クリック数を最小化し、組織選択だけで必要指標が出るレイアウトに徹底。現場の「触りやすさ」が利用拡大を生む。 - 共通指標で“文化の壁”を崩す
営業と経営が別々の数字を追う状況を、SJ-R が定義した共通 KPI で統合。トップライン偏重文化を脱却し、データに基づく行動変革サイクルを構築。 - ROI は「コスト減・効率化・売上増」の三本柱で算出
グループ CFO が納得する指標体系を先に型化し、効果説明の手間を削減。
失敗しないための教訓
- KPI を最初に作り込み過ぎない
見えない ROI を議論するより “まず動かす” 方がデータ文化は早く根付く。 - UI/UX への投資を後回しにしない
見にくいダッシュボードは利用されず、結局エクセルを使うようになってしまう、といった問題を解決。 - 指標の改定を恐れない
KPI は複数回見直しして、運用の中でブラッシュアップする姿勢が必須。

データ分析立ち上げにおける海外企業の事例
また海外企業のデータ分析立ち上げ事例に関しても紹介していきます。
Netflixの事例
Netflixは今や誰もが知る動画配信サービスです。
もともとは1997年に設立されたDVDのレンタル事業を行っている会社でしたが、ストリーミングサービスへの移行、オリジナルコンテンツ制作をベースにして、最先端の技術も取り入れたレコメンドエンジンにより売上を伸ばしていった会社になります。他社競合よりも圧倒的にデータ活用に特に力を入れて大規模なDXを達成した事で、成功した企業の一つとも言えます。
高度なパーソナライズ推薦システム
Netflixは特にパーソナライズ推薦システムに力を入れています。
昔からデータサイエンティストをやっていた方はご存知かもしれませんがNetflixの有名なデータ活用の事例として、Netflix Prizeと呼ばれるデータ分析コンペティションを開催し、100万ドルの賞金を出し、優れた協調フィルタリングアルゴリズムのコンペを行いました。
当時としては事例もなかなかない中、Netflix社内だけではなく、外部の高度なデータサイエンティストの知見も取り入れ、独自のアルゴリズムよりも10%以上精度が高いアルゴリズムを導入し、データサイエンス界隈でもビジネス界隈でも話題となりました。今では視聴アクティビティの80%は、パーソナライズレコメンドによって発生しているようです。
また、有名な別の事例としては、各ユーザーの視聴傾向に応じて、同じ作品でもユーザーによって表示されるサムネイル、予告編をパーソナライズ化したことにより、顧客満足度向上につなげています。例えば、恋愛傾向を好むユーザーには恋愛シーン中心のサムネイルや予告、アクション映画を好きなユーザーに対しては、アクション関連の内容を強調した予告を提示する、といった事によりパーソナライズされたレコメンドを行い、クリック率を30%向上させる、といった細かい機械学習の最適化がビジネスの売上に直結しています。
では、どのぐらいこのパーソナライド推薦システムが影響しているでしょうか?

上記の記事では、Netflixはこの独自の推薦エンジンにより「少なくとも10億ドル以上」の顧客維持収益を生み出していると明言されています。また、Netflixの月次解約率も異例の2.3%-2.4%とされており、業界平均の5%-6%と比較すると、圧倒的に低い事がわかります。
広範囲にわたるABテスト文化
A/Bテストとは、ある要素の効果を比較・検証するために、2つ以上のバージョン(主にAパターンとBパターン)を用意し、ユーザーにランダムに表示させて、その結果を比較する手法です。主にマーケティングやUI/UX改善、Webサイト最適化などで使われます。
NetflixではUIのボタン配置、作品横並び順、プロモーションの文言、サムネイルのバリエーションを決めるアルゴリズム、あらゆる要素でA/Bテストを実施し、定量的に効果を検証し、最適化しています。簡単に効果が出た分かりやすい例で言うと、”Play Next”のボタンの位置を調整しただけで、エピソード継続視聴率が20%アップしたような効果もあったようです。
特にアメリカの大手企業はわずかな効果増加が見込めるだけでも売上に直結しやすいため、A/Bテストを重要視しています。私が在籍していたMicrosoftでも才能豊かな研究者がA/Bテストの基盤を作成しており、A/Bテストの文化がエンジニア/PMなどにも定着しており、A/Bテストのおかげで毎年増加する売上を達成できていたように思います。
A/Bテストに関して、もっと詳しく知りたい方はこちらの本がおすすめです。
データを活かしたコンテンツ戦略
Netflixのデータ活用の独自性の面白い例として、データを活かしたコンテンツ製作というものがあります。
Netflixの有名なドラマの一つに「House of Cards」という政治ドラマがあります。実はこのドラマはユーザーの視聴データに基づいて、パイロット版も作成せず、多額の投資をして作成されていました。
このドラマが予想を超える大ヒットをした事で、内容ではなくて「視聴者データ」からコンテンツを製作する、というオリジナル製作戦略の転換点となったようです。
配信前のコンテンツ製作でも生かされていますが、配信後の高度な視聴分析をして続編や同様ジャンルの企画判断にも影響を与えているようです。例えば、「イカゲーム」などもデータ分析を活かし、続編の意思決定がされているようです。
Walmartの事例
Walmart(ウォルマート)は日本ではあまり馴染がないですが、アメリカ合衆国に本社を置く世界最大の小売業者であり、グローバルに展開するスーパーマーケットチェーンです。Netflixと同様に機械学習のコンペティションで有名なため、データサイエンティストの方はご存知かもしれません。
リアルタイム情報共有と在庫最適化
Walmartは古くからある会社ですが、比較的昔からデータ活用に力を入れており、1990年代からRetailLinkと呼ばれるプラットフォームを構築して、仕入先との売上および在庫データをリアルタイムで共有できるシステムを実現していました。また、最新の2025年でもRetailLinkは進化しており、在庫管理の精度向上・需要予測精度向上・サプライヤー調整を改善しており、仕入先の最適化による競争優位性強化を行っています。
また、非公式ではありますが、第三者機関の事例報告による、リアルタイムデータ分析を導入した事で、物流コスト10%削減、欠品率16%削減、在庫回転率の向上、などデータの利活用により、売上・顧客満足度の向上を実現しています。
物流最適化・リアルタイム配送可視化
スーパーには配送が付き物ですが、配送スケジュールの最適化、リアルタイムの出荷追跡・可視化プラットフォームを社内で構築し、配送状況の監視・予測分析・自動アラートなど、他社と比較してパフォーマンスの高い輸送効率を実現しています。
データ分析の企業事例から考える成功要因・失敗要因
記事の前編と少し内容がかぶってきますが、ここまで大企業の事例を見てきたので、データ分析の事例から考えられる、特に重要なポイントをまとめていきたいと思います。
データ分析で成果を出すために特に重要なポイントとしてはやはり
- データの民主化
- 専門家以外でも、「誰もがデータを使える状態」を実現する。
- ビジネスと密接に連携したチーム設計
- 分析支援するだけではなくて、意思決定への影響が出来るようなデータ分析推進を行う。
- ABテストによる仮説検証文化の定着
- 改善の施策を行う際、売上に直結する形で、定量的なA/Bテストを行う。
- PoC主導で“まずやってみる”文化
- 何よりもスピードを重視し、PDCAを回し、段階的に少しずつスケールさせていく。
逆に失敗してしまう例としては
- KPIを最初から厳格に決めすぎる
- 柔軟に組織やKPIを変更していかないとKPIの策定に時間がかかってしまい、PDCAの速度が遅くなる。
- 目的のない分析を行ったり、全従業員に使われないダッシュボード・AIを作らない
- よくある失敗例として、導入した(作成した)ダッシュボードやAIが使いづらく、元のやり方に戻す、という例があるため、使われるようにする、もしくは社員のデータ活用・AIリテラシーを上げる。
- 専門部署だけでの体制にしない
- 分析チームが使われない分析に終わってしまうパターンがある。また、他部署から見たときに何をしているか分かりづらいという点があるため、他チームとも連携を進めていく必要がある。
- 共通指標の不在
- 現場と経営層でも同じ数字を見るようにデータ基盤を整える。別の数字を見る事で意思決定がバラけてしまうので、全社で見るべきKPIの統一が必要。
まとめ
データ分析チームの立ち上げと成功は、明確な目的設定、多様なスキルを持つバランスの取れたチーム、適応性のある組織構造、強力な経営層の支援、浸透したデータドリブン文化、価値に焦点を当てた実践的なロードマップ、そして成功と失敗の両方からの継続的な学習といった、多くの重要な要素に依存します。
データ分析チームの立ち上げとスケーリングは、時間もコストもかかり、費用対効果を期にしなければなりませんが、ほとんどの企業は継続的に売上を拡大していく必要があるため、データ分析・AIの導入は必須になります。特に最近はLLMなどの生成AIが進化をしていき、多種多様な業界でどんどん導入されています。
競合他社がデータ分析を導入し拡大している中で、自社だけデータ分析/AIの施策を導入していない、となると、やはり長期的には淘汰されていくリスクが高いです。
データ分析チームの立ち上げは単に技術的な能力を組み立てるだけではなく、組織がどのように考え、運営し、意思決定を行うかを根本的に変革することです。この記事では実践的に企業の成功事例、失敗事例を見て、学べる事を記事にしてみました。