データ分析チーム立ち上げ完全ガイド(中編):4STEPで実施する分析チームのロードマップ
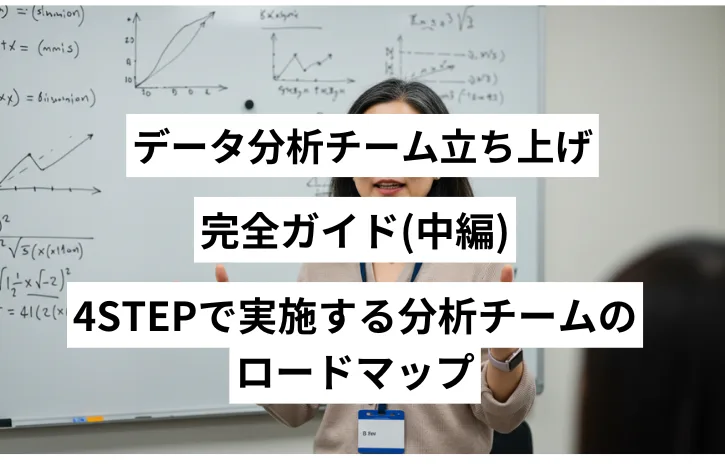
こんにちは!サステックスの代表、須藤です。
本記事は前編、中編、後編にまたがった「データ分析チーム立ち上げ完全ガイド」の中編の記事となります。
前編の記事はこちらになります。
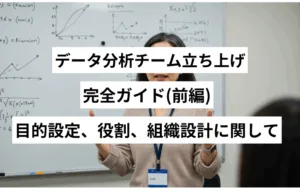
前編ではデータ分析チームの具体的な役割、データ分析チームの組織体系、初期分析チームの立ち上げ規模に関して記載していきました。中編では立ち上げたデータ分析チームが行っていく分析の具体的な進め方に関して解説していきます。後編では具体的な企業のデータ分析チームの成功事例、失敗事例に関して紹介していきます。
データ分析プロジェクトの成否を分ける「最初の壁」
多くの企業がデータ分析でつまずく最大の理由は、分析プロセスを開始する前の「目的」「評価」「進め方」の解像度が低いことにあります。
いきなりデータ分析を始めるのではなく、まずはロードマップの全体像を把握しましょう。本記事で紹介する4ステップは、分析版のPDCAサイクルとも言える「PPDAC(Problem, Plan, Data, Analysis, Conclusion)」サイクルをベースにしており、多くの成功プロジェクトで採用されているフレームワークです。
4STEPで実施するデータ分析チーム実践ロードマップ
データ分析チームを社内で立ち上げた事が出来たら、次は実際に分析のプロセスに進んでいきます。
データ分析チームの立ち上げ時に最も大切な事は「目的」「評価」「進め方」を明確にしておくことです。
本記事では、実践的な4ステップで進めていき、ビジネス価値につながるデータ分析を行っていく事が出来ます。

STEP1:ゴール設定と計画
最初のステップでは課題の特定、ゴールの設定、評価指標の決定、仮説の構築を行います。
当たり前のプロセスと思われるかもしれませんが、よくあるケースとしては中小企業がデータ分析チーム・DX推進部を立ち上げたものの何をして進めれば良いか分からない、といったケースも実際に多くの現場で見られています。
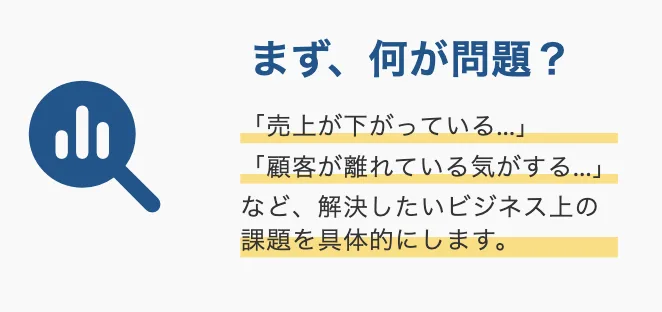
課題の特定
どんなビジネス課題を解決したいのか、どんな意思決定をサポートしたいかを明確にする。
例
- 「ECサイトの特定カテゴリ商品の売上が、前年比で20%減少している」
- 「最近投入したマーケティングキャンペーンの効果が不明で、来期の予算配分を判断できない」
- 「コールセンターへの問い合わせ件数が急増し、オペレーターの業務が逼迫している」
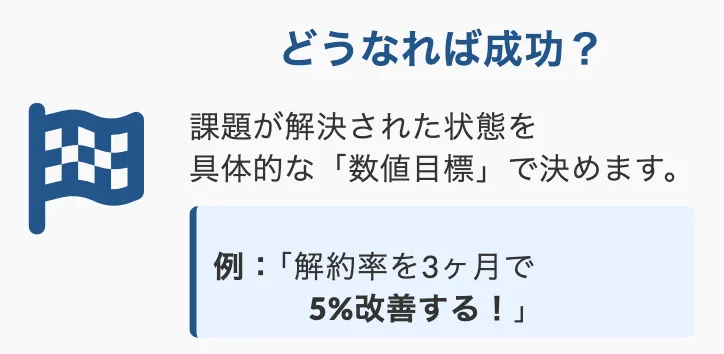
ゴールの設定
課題がどうなれば「成功」と言えるのか、測定可能な数値目標(KPI)を具体的に設定する。
例
- 「3ヶ月以内に、対象カテゴリ商品の月間売上を前年同月比プラスマイナス0%まで回復させる」
- 「キャンペーン経由での新規顧客獲得単価(CPA)を、目標値である5,000円以下に抑える」
- 「WebサイトのFAQページ改善により、製品Aに関する問い合わせ件数を2ヶ月で30%削減する」
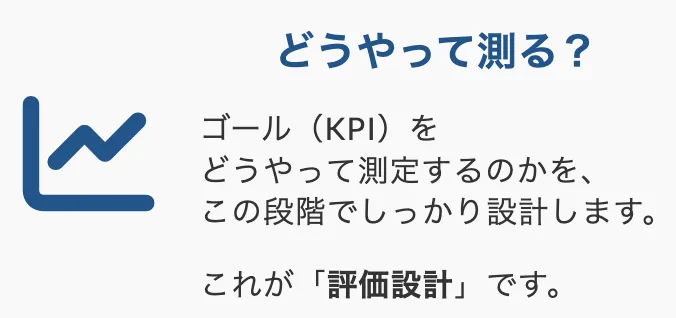
評価方法の決定
設定したゴール(KPI)を、どのデータを使って、どのように計算・測定するのかを具体的に定義する。
例:
- 「販売管理システムの売上データから、毎週対象カテゴリの売上額を抽出し、前年同月の売上額と比較する」
- 「広告プラットフォームのデータと自社の顧客DBを連携させ、『キャンペーン広告費 ÷ 新規顧客数』で日次のCPAを算出・レポートする」
- 「問い合わせ管理システムのデータから、製品Aに関する問い合わせ件数を週次で集計し、施策開始前の平均値と比較する
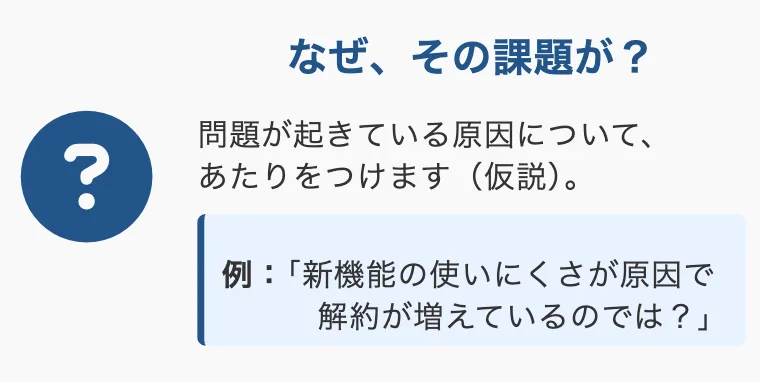
仮説の構築
なぜその課題が起きているのか、考えられる原因について「仮の答え(仮説)」を立てる。
例:
- 課題(売上減)に対して: 「競合他社が同じカテゴリで大規模な割引を行ったため、顧客が流れているのではないか?」
- 課題(キャンペーン効果不明)に対して: 「ターゲティング設定が広すぎ、製品に関心のない層へ広告が配信され無駄なコストが発生しているのではないか?」
- 課題(問い合わせ増)に対して: 「先月のアップデートで追加された新機能の使い方がマニュアルだけでは分かりにくく、操作方法の質問が殺到しているのではないか?」
STEP2:データ準備・整形と分析
次に、実際のデータを扱っていく作業になります。まず、必要なデータを収集し、分析に適した形式に整える作業が必要となります。多くの企業ではデータ分析を視野に入れたデータ基盤設計になっていない事が多いため、実際には泥臭い作業が必要になることが多いです。例えば、表記揺れが発生して名寄せが必要になる、IDの連携が出来ない、アクセスのために別チームの許可申請に時間がかかる、といった点が挙げられます。
そして、整形されたデータから意味のある情報を抽出して、仮説を検証出来るような統計的分析手法や可視化、機械学習モデルの構築などを行っていきます。このSTEPではデータエンジニアにより、分析基盤を整えて分析が行いやすい環境の構築をしたり、データサイエンティストによる分析を行っていきます。
また、継続的なデータ分析を行うために、前回の記事でも紹介したデータランドスケープに関して、こちらのSTEPで可視化してと良いです。
より詳しい役割に関しては、前回の記事に記載しています。
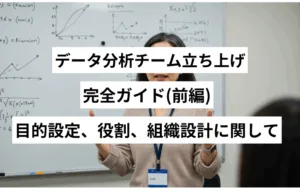
STEP3:考察とアクションプラン策定
STEP2で実施された分析結果を元に、ビジネス的な解釈、次のアクションの選定を行っていきます。
よく受託のデータ分析プロジェクトではエグゼクティブサマリーとして、分析結果を意思決定者に分かりやすく伝える事がありますが、考察を含めてデータサイエンティストとしての力量が問われる箇所になります。
考察を踏まえて、次のアクションプランを考えていく上で、具体的にどのような改善・アクションプランを行っていく、という箇所はデータサイエンスのスキルだけではなくて、ドメイン知識(事業に必要な知識)も必要となってくるため、ビジネス側の方と協力して、次のアクションを複数考えて、最適な施策を絞り込んでいく必要があります。
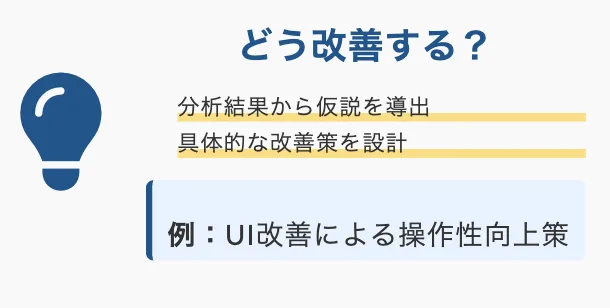
例
「新機能はユーザーに分かりづらかったため、チュートリアルを実施してユーザーに分かりやすくする」など。
STEP4:実行と効果検証
STEP3で決めたアクションプランを実行していき、STEP1で決めたKPIにより、施策の効果を測定していきます。
施策がうまくいった場合、なぜうまく行ったのか、を分析して横展開、別のプロジェクトに展開出来ないか、という点を考えて行きます。上手くいかなかった場合は次の仮説、アクションプランを行っていき、数をこなしていく事で質の高い仮説設定、質の高い施策提案を行っていく事が出来ます。
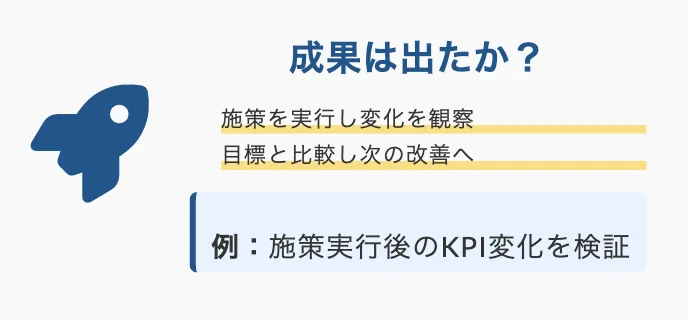
まとめ
本記事では、データ分析における具体的なプロセスを4STEPに分けて記載しました。ごくごく当たり前のプロセスを記載しましたが、データ分析では基本的な事を確実に進めていき、定量的に改善していく姿勢がとても重要です。
後編では実際の国内・国外企業のデータ分析チームの成功事例と失敗からの教訓をまとめていくので、よければそちらの記事もご覧ください!


