【2025年度版】失敗しないシステム開発会社の選び方|プロが教えるチェックポイントとAI駆動開発によるシステム開発
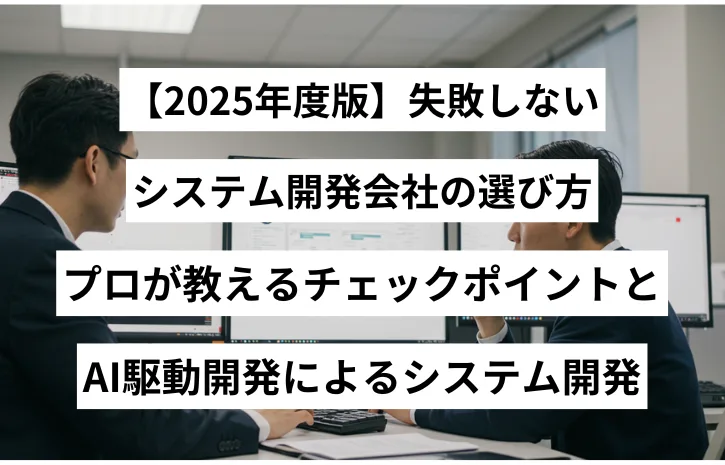
サステックスのAIエンジニアの須藤です。
社内でシステム開発が出来ない会社の場合、システム開発を外注する機会があると思います。システム開発プロジェクトの成功可否は依頼する開発会社の選定に大きく左右されます。そして、思っているよりもシステム開発は失敗に終わるプロジェクトが多いです。
とある記事によると、国際的な調査「CHAOS Report」の2020年度版の調査では、約50000件のシステム開発プロジェクトの66%のプロジェクトが「失敗、または部分的な失敗」に終わるとされています。また、成功とされたプロジェクトはなんと全体の31%しかなかったそうです。

また、国内の調査『企業IT動向調査報告書2021』の2021年度の調査では、大企業を中心とした約4,500社対象に、短規模プロジェクト(100人月未満)での納期・予算・品質の達成率などが分析されましたが、同様に成功率が約30%とされているため、国内・国外ともに3割のプロジェクトしか成功していない、という事が分かります。
多額の費用と時間を投じるシステム開発だからこそ、「絶対に失敗したくない」というのが発注側の本音でしょう。本記事では2025年最新の情報を踏まえ、失敗しないシステム開発会社の選び方を解説します。特に今年はCursorやGithub CopilotなどAIコーディングエージェントが進化してきた事で大きくシステム開発にも技術的な革新が起きています。
選定時に確認すべきポイントから、事前準備や注意点まで網羅的に紹介するので、システム開発会社選びに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
失敗しないシステム開発会社選びのポイント
システム開発会社を選定する際、以下のポイントを押さえておきましょう。
それぞれがプロジェクト成功率に直結する重要事項です。
開発実績と得意分野を確認する
まず注目したいのがシステム会社の開発実績です。過去にどんなシステムを手掛けてきたかを確認することで、その会社がどの分野・業界に強みを持つか把握できます。ポイントは、実績の「数」よりも内容の適性です。単に実績件数が多いだけでなく、自社が開発したいシステムと同種のプロジェクト経験が豊富かを重視しましょう。
例えば業務管理の社内システム開発が得意な会社と、一般消費者向けのWebサービス開発が得意な会社では全く強みが異なります。自社のニーズに合った実績を持つ会社なら、業界特有の要件や必要な機能を理解しているため安心です。
次に得意分野も確認しましょう。開発会社ごとに「医療系システムに強い」「金融業界に詳しい」「〇〇言語が得意」「アジャイル開発を積極採用している」など特色があります。
公式サイトの実績ページやサービス紹介を見る事で、その会社が力を入れている分野・技術が分かりやすいかと思います。実績豊富でも自社が望む分野が不得意だと、期待通りの成果にならない可能性があります。なお、公式サイトに実績事例が掲載されていない場合も多々あります。守秘義務の関係で公開できない実績もあるためです。
そのため、問い合わせ時に「過去に〇〇の開発経験はありますか?」と直接尋ねてみましょう。過去の事例で得られた効果(売上〇%向上など)が聞けるとベストです。実績の公開有無に関わらず、自社が望むシステムに近い開発経験がある会社を選ぶことが、失敗しないための第一歩です。
また、最新トレンドを追い活用できている会社かどうかも、技術力を測る指標になります。例えば、ブログやSNSで技術情報を発信している会社は、技術力・業界知識が豊富で常に最新情報をキャッチアップしている傾向があります。
特に今年2025年では、AIの進化がとても進んできており、システム開発時にもコーディングエージェントやAIを活用したシステム要件の整理、など技術的な革新が起きているため、今までの開発を行っている企業とAI駆動開発を行っている企業だと作業効率が全く変わってくるため、この観点も重要な観点になってきます。
開発会社の規模・体制と経営安定性をチェック
次に、その企業自体の規模や経営状態、開発体制も重要な判断材料です。
システム開発は開発期間が長期に及ぶうえ、納品後も継続したサポート関係が続くため、依頼先には安定して事業を継続できる体力が求められます。具体的には、創業からの年数や資本金、主要取引先、直近の業績推移などを確認するとよいでしょう。上場企業や大手のグループ会社であれば信頼性は高いですが、中小でも黒字経営を続けていたり資金調達実績がある会社は信頼できます。逆に極端に規模が小さかったり設立間もない会社に大規模開発を依頼する場合、納品前に倒産…など最悪のリスクもゼロではないため注意が必要です。 開発体制についても把握しましょう。自社にエンジニアを多く抱え自社開発中心で行っている会社もあれば、プロジェクトの多くを下請け企業に再委託する「元請け」的な会社もあります。
また、在籍エンジニアのスキルやコミュニケーション効率の面では、自社内で完結する比率が高い会社の方が一貫した品質を担保しやすい傾向にあります。
しかし実際には、大半の開発会社が不足リソースを外部パートナーで補完しているのが実情です。外注そのものは決して悪いことではなく、開発会社側が品質と進行をしっかり管理していれば問題ありません。重要なのは「自社開発かどうか」そのものより、最終的な品質責任をきちんと負ってくれるかです。打ち合わせで「開発は全て自社で対応しますか?一部外部協力はありますか?」と尋ね、もし外注先を使う場合でも契約上の責任は依頼先企業が負うことを確認しておきましょう。品質担保の姿勢が曖昧な会社は避けるのが賢明です。
また、プロジェクトマネジメント手法や開発プロセスも体制面でチェックしたいポイントです。ウォーターフォール型で一括請負の場合は、最初の要件定義が肝心になりますし、アジャイル開発を取り入れている会社であれば、要件変更への柔軟な対応力が期待できます。どちらの手法にせよ、進捗の見える化や定期報告の仕組みを設けている会社だと安心です。例えば週次ミーティングやタスク管理ツールで状況共有してくれるなど、開発の透明性が高い会社を選ぶとよいでしょう。
ちなみに先程紹介した「CHAOS Report」ではアジャイル型の開発の方がウォーターフォール型開発と比べて成功率が3倍高い、とされているため、もし要件が定まっていない場合はアジャイル型の開発の方が一般的には良いとされています。
契約前の打ち合わせ段階で、開発フローや報告頻度について質問し、明確に答えられる会社かどうか見極めてください。
担当者のコミュニケーション力と提案内容を確認する
また、実際にプロジェクトを進めていく上で、担当者(窓口となる営業やPM)の人柄・コミュニケーション能力は極めて重要です。どんなに技術力の高い会社でも、担当者との意思疎通がうまくいかなければ要求通りのシステムは出来上がりません。初回の問い合わせや見積もり相談の段階で、「対応が迅速かつ丁寧か」「こちらの話を正確に理解しようとしているか」を確かめましょう。返信までの速さや提案資料のわかりやすさなどから、その会社の顧客対応レベルがうかがえます。専門用語ばかり並べるのではなく、素人にも理解できる言葉で説明してくれる担当者なら、コミュニケーション面で信頼できます。 また、こちらの要望に対する提案内容もチェックポイントです。ヒアリングを通じて自社の課題や目的をどれだけ理解し、適切な解決策を提示してくれるかを見極めましょう。
例えばこちらが漠然と「使いやすい販売管理システムが欲しい」と伝えたときに、単に「承知しました」ではなく「現場のどんな課題を解決したいですか?」と掘り下げて聞いてくれたり、「在庫管理機能も含めれば二重入力を減らせるかもしれません」とプロの視点で提案してくれる会社は頼もしいパートナーと言えます。逆に要望をそのまま鵜呑みにするだけで疑問を投げかけてこない場合、プロジェクト進行後に認識ズレが生じるリスクがあります。システム開発では「なぜその機能が必要なのか」を双方で深く議論し、要求をブラッシュアップしていく姿勢が成功の近道です。 さらに、担当者との相性も無視できません。長期プロジェクトになるほど、人間同士の信頼関係が大切です。打ち合わせ時の受け答えや雰囲気から、「この人になら任せられる」「一緒に問題解決していけそうだ」という感触が得られるかを大事にしてください。プロジェクトへの熱意を持って寄り添ってくれる担当者かどうかは、メールや商談時の姿勢で意外と見えるものです。こうしたソフト面も含めて総合的に判断すると良いでしょう。コミュニケーション不足はシステム開発失敗の大きな原因となるため、「伝えたいことを正しく伝える」ために信頼できる担当者を選ぶことが、失敗しない会社選びの要です。
納品後のサポート体制を確認する
システム開発は納品がゴールではなく、その後の運用・保守フェーズまで含めて初めて成功と言えます。導入したシステムを長く安定稼働させるためには、開発会社のサポート体制が極めて重要です。納品後に不具合が見つかった場合の対応、機能追加や改修の相談、操作方法に関する問い合わせ対応など、どこまでサポートしてもらえるのか事前に確認しましょう。 具体的には、以下の点をチェックしてください。
保守サービスの内容
定期メンテナンスやアップデート対応、障害発生時のトラブルシューティングなど、提供される具体的なサポート内容を確認します。契約範囲内で無償対応してくれる内容と、有償オプションになる内容を仕分けて把握しておきましょう。
サポート対応時間
平日昼間のみ対応なのか、夜間・休日もエンジニアが待機しているのか。システムの重要度によっては24時間365日のサポート体制が必要なケースもあります。自社の運用に合った体制ができるかどうか確認します。
問い合わせ窓口
専用のサポートデスクやチャットサポートがあるか、担当者経由になるのか。問い合わせ方法(電話・メール・チケットシステムなど)やレスポンスの速さも重要です。
保守費用
月額保守料やスポット対応費用など、コスト面も契約前に明確にしておきます。最初の見積もり段階で「保守費用はどの程度を想定すべきか」と尋ね、年間ランニングコストを把握しておきましょう。
特にシステム開発に不慣れな企業ほど、導入後のフォローが手厚い会社を選ぶことが肝心です。「納品して終わり」ではなく長期的なパートナーとして付き合える会社だと安心して運用できます。仮に開発と保守を別会社に分ける場合は、引き継ぎの範囲や責任の所在が明確になるよう契約書に定めてもらいましょう。いずれにせよ、運用フェーズまで見据えて会社選びをすることが失敗しない秘訣です。
複数社の見積もりを比較し、費用対効果を検討する
最後に費用面ももちろん重要なポイントです。ただし単に安さだけを追求するのは危険です。システム開発は品質とコストが比例しやすい領域で、優秀なエンジニアほど単価が高いものです。極端に安い見積もりの会社は、担当エンジニアのスキルや経験が不足している可能性があり、結果的に品質の低いシステムが納品されてしまうリスクがあります。実際、「費用が安いからと依頼したら期待はずれの成果物だった」「後になって追加費用を請求された」という失敗例も少なくありません。 そうならないためにも、複数社から相見積もりを取り比較検討することが大切です。一般的には3~4社程度に相談し、提案内容と見積金額を比較しましょう。
その際、以下の点に注目して検討します。
見積もりの内訳
各社の見積もりごとに、人件費(工数)やソフトウェアライセンス費、サーバー費用など項目ごとに明細が出ているかどうか、を確認しましょう。
提案内容との整合
各社で提案してくるシステムの範囲が違えば金額も異なります。提案A社は機能を絞ってコストを抑えている一方、B社は将来の拡張も見据えて高機能な提案をしているかもしれません。自社の優先順位(予算重視か、多少高くても高品質重視か)を踏まえ、単純な額面比較にならないよう注意しましょう。
費用対効果(コストパフォーマンス)
最も重要な点になりますが、システム開発が提示金額に見合う価値が得られるかを考えます。他社より高額でも、実績豊富で安心感が高かったり、充実したサポート込みで長期的にはお得になるケースもあります。逆に安くても社内工数が増えてしまえば本末転倒です。総合的なコスパを評価しましょう。
見積もり比較で悩んだときは、各社に気になる点を遠慮なく質問する事が大切です。
「この機能を省けば予算内に収まるか」「納期を優先すると費用はどう変わるか」など相談し、納得いくまで交渉しましょう。契約前の段階で費用と成果物の範囲を明確にすり合わせておくことが重要です。
契約書には納品物の範囲や支払い条件、保守の有無、納期遅延時の対応などを盛り込み、後から「聞いていない」とならないようにします。費用は大事な判断基準ですが、「安さ」だけで選ばず総合力で判断することが、失敗しない会社選定の鉄則です。
システム開発会社に依頼する前の準備ポイント
上記のポイントを踏まえつつ、発注側で事前に準備しておくべきこともあります。十分な準備をして臨むことで、開発会社とのミスマッチやプロジェクトの行き違いを防ぐことができます。
依頼前に以下の点を確認・整理しておきましょう。
目的・課題を具体化し共有する
なぜそのシステムが必要なのか、導入によって何を達成したいのかを明確に言語化します。「業務効率を〇%改善したい」「〇〇の手作業を自動化したい」など具体的なKPIや課題を定めておきましょう。目的が曖昧なままだと、出来上がったシステムが理想と異なる結果になりがちです。社内の関係者間でも目指す方向性を事前にすり合わせ、開発会社にきちんと伝えられる状態にしておきます。
要求機能・条件を整理する
必要な機能リストや利用ユーザー、連携が必要な既存システム、セキュリティ要件など、可能な範囲で具体的な要件を書き出します。特に「これだけは外せない機能」や逆に「将来的に追加できればよい機能」など優先度も付けておくと、提案を受ける際に比較検討しやすくなります。可能であれば提案依頼書(RFP)を作成し、目的・要件・予算・納期などを一つの資料にまとめるのがおすすめです。RFPがあれば数社から統一条件で提案を引き出せ、比較も容易になります。
全体予算とスケジュールを決めておく
システム開発そのものの費用だけでなく、関連するハードウェア費用やライセンス料、運用開始までの教育コストなども含めて予算枠を検討します。あわせて、希望する納期(リリース時期)も社内で合意しておきましょう。「なるべく早く」といった漠然とした希望ではなく、「〇年〇月までに稼働開始したい」など明確に伝えます。ただしスケジュールには必ず余裕を持たせることも重要です。開発が完了しても、その後のテストや不具合修正、ユーザー教育期間も必要になります。無理のない計画を立てることで、納期に追われて品質が疎かになるリスクを減らせます。
社内体制の整備
発注側でもプロジェクトを管理する担当者や意思決定フローを整えておきます。開発会社との打ち合わせには業務に詳しい現場担当者にも参加してもらい、要望の漏れや認識違いを防ぎましょう。「誰が最終的に仕様を決定するのか」「問い合わせやレビューの窓口は誰か」を決めておくことで、開発会社とのコミュニケーションが円滑になります。また、最低限のITリテラシーや専門用語の理解も担当者には必要です。発注側に知識がないとコミュニケーション不足に陥りやすいため、必要に応じて事前勉強や外部コンサルの助言を受けることも検討しましょう。
複数社とコンタクトを取る
具体的に相談する候補の開発会社をリストアップしておきます。社内や知人の紹介、Web検索、マッチングサービスの活用などで3~5社程度に絞り、順次アプローチしましょう。一社だけで即決せず、複数の会社の話を聞くことで視野が広がり、適正な相場観も養われます。日程調整や秘密保持契約(NDA)の取り交わしなど、実際に相談を始める前の段取りも計画しておくとスムーズです。
事前準備を万全にしておけば、開発会社選定から要件定義までのプロセスが格段に進めやすくなります。「準備不足」はシステム開発失敗の代表的な原因でもあるため、発注側でできる限りの検討を重ねてから依頼に臨みましょう。
失敗しないための注意点と心構え
最後に、開発会社選びやプロジェクト進行において特に注意すべきポイントをまとめます。以下の点を意識するだけでも、失敗のリスクを大きく減らすことができます。
費用だけで外注先を選ばない
繰り返しになりますが、価格の安さだけで判断するのは危険です。特に相場より極端に安い提案には裏があるものと考えましょう。費用面は大事な要素ですが、実績や提案内容、サポート体制まで含めた総合評価でパートナーを選定してください。
開発を丸投げにしない
発注後、「任せておけば自動的に良いものができるだろう」とすべてを開発会社に丸投げしないことも重要です。システム開発では、仕様の行き違いや予定遅延など想定外の事態が起こりえます。進捗確認やテストへの立ち会いなど、発注側も適度に関与しましょう。
こまめに状況を把握していれば、ズレが生じても早期に修正できます。特に近年はアジャイル開発を採用する会社も増えており、開発途中での仕様すり合わせがしやすくなっています。。任せきりではなく一緒にプロジェクトを作り上げる姿勢が成功に繋がります。
無理のないスケジュールを設定する
要求する納期が非現実的な急ぎの案件だと、プロジェクト失敗の確率が高まります。納期を急ぎすぎると、結果的に品質低下や追加コストの発生につながる可能性があるためです。当初計画より多少遅れても許容できるくらいのバッファを持ったスケジュールを組みましょう。どうしても期限ありきの場合は、機能範囲を絞る・リリース後に改良を続けるなど柔軟な計画で対応します。時間・品質・コストのバランスを意識し、優先順位を明確にして臨むことが大切です。
契約条件・責任範囲を明確にする
開発会社を選定したら、契約書の内容もしっかりチェックしましょう。納品物の定義、検収条件、支払い条件、知的財産権の扱い、不具合発生時の修正対応や保証範囲など、曖昧な点が残らないようにします。特に下請けを使うケースでは、最終的な責任を依頼先企業が負うことを契約上明記することが重要です。万一トラブルになっても責任の所在が明確なら対処しやすくなります。必要に応じて専門家(行政書士や弁護士)に契約書のリーガルチェックを依頼するのも一案です。契約段階でしっかり詰めておけば、開発途中の認識相違による揉め事を防ぎ、安心してプロジェクトを進められます。
以上の点に注意しつつ、適切な準備とパートナー選びができれば、システム開発プロジェクトの成功率は格段に高まります。昨今のDXブームで多くの企業がシステム開発に取り組んでいますが、その明暗を分けるのは会社選びとプロジェクト管理と言っても過言ではありません。費用の安さや知名度だけで飛びつかず、本記事で紹介したような多角的な観点で候補を比較検討してください。
2025年、システム開発は「AI駆動開発」による革命期へ
冒頭でも説明しましたが、今年2025年は特にAIの進化が凄まじく、システム開発においても圧倒的な効率化や品質向上ができるようになってきています。様々な手法がありますが、最も有名なのはAIコーディングエージェントの活用になります。
AIコーディングエージェントについては、別記事で詳しく説明を行いますが、たとえば、Cursor・GitHub Copilot・Devinといったツールは、すでに多くのエンジニアに活用されており、名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
そして、「AI駆動開発」と呼ばれる手法も進化してきており、多くの事業会社に導入されてきています。
AI駆動開発によるメリット
AI駆動開発とは、要件定義・設計・実装・テスト・運用といったシステム開発の各プロセスにおいて、AI技術を活用するアプローチです。従来の自動化とは異なり、生成AIや機械学習を用いて「人間と共同で考え、生成し、判断する」フェーズが含まれます。
AI駆動開発にはエンジニアや開発会社だけではなく、発注者にも多くのメリットがあります。例えば、
- 要件定義の精度が向上し、認識ズレや手戻りが減る
- 仕様や工程の可視化が進み、進行状況を把握しやすい
- 開発スピードが加速し、納期が短縮される
- コストが最適化され、開発費用を抑えやすくなる
- 品質が担保された状態でリリースできる
つまり、簡単に言うと「納期が早く」「費用も安く」「高品質」なシステム開発ができるようになってきています。
そのため、これからシステム開発を検討している企業にとっては、AI駆動開発に取り組んでいる開発会社を候補に入れることが、より良い成果を得るためのひとつのポイントになるでしょう。
とはいえ、AI駆動開発にはすべてがメリットというわけではありません。
いくつか注意すべきデメリットも存在します。
AI駆動開発によるデメリット
AIを活用するスキル+エンジニアとしてのスキルが必要
短期的なシステムであれば、非エンジニアでも開発が可能になってきていますが、長期的なシステム開発ではAIの出力結果を正しく判断できる基礎エンジニアリングのスキルが必要となっています。そのため、ある程度の規模のシステムを開発する上では、AI活用が出来るスキルを持つエンジニアが必須になります。
実際にロイター社の記事では、熟練ソフトウェア作業社でもAIをうまく使いこなす事が出来ない場合、逆にAIを使用する事で作業時間が増加してしまっているといった調査も出てきています。

長期的なコード品質の管理
生成AIはコードの生成は得意でも、長期的なコード品質の管理が難しい、というデメリットもあります。例えば、短期的には動作するコードが出来たとしても、全体としてツギハギコードが多くなってしまい、長期的な運用が難しくなっていく、という問題があります。
誤った提案をそのまま採用すると、システムの品質やセキュリティにも悪影響が出る可能性があります。
サステックスはAI駆動開発のプロフェッショナル集団です
弊社サステックスは元Microsoftのソフトウェアエンジニアが創業し、AI技術とシステム開発の融合に強みを持つ技術集団です。
代表をはじめとするエンジニア陣は、AI・統計・自然言語処理・データ分析・生成AIなど多分野に精通しており、これまでに200件以上のAI活用支援を成功に導いてきた実績があります。一般的な「CopilotやDevinを使っている」という粒度ではなく、要件定義・プロトタイピング・実装・テスト・運用に至るまで、AIを中核に据えた開発体制を標準としています。
AIによる仕様作成支援・要件抽出・テストコード生成・長期的に運用がしやすいコードの作成など、全体を通して、プロジェクト全体の速度と成功率を大きく高めることを可能にしています。また、AI導入にありがちな「手戻り」や「ブラックボックス化」も、エンジニアによる技術判断と品質管理で丁寧に対応しているため、AI駆動開発でありがちな短期的な動作だけのコードではなくて、中長期的にメンテナンスしやすい設計思想を大切にしています。一方で、短期的なPoC(実証実験)を行いたい場合は、AI駆動開発の強みを活かす事で、圧倒的に納期が早いプロトタイプの開発が可能です。
「システム開発を外注したい」「AIの力を使って高速かつ低コストでシステムを構築したい」「実装だけでなく仕様段階から相談したい」といったご要望があれば、まずはお気軽に弊社にご相談ください。小規模なPoC(実証実験)から、エンタープライズ向けの本格開発まで、柔軟にご対応いたします。
まとめ:開発会社選びがプロジェクト成功のカギ
システム開発は、どの会社に依頼するかでプロジェクトの結果が大きく変わります。
本記事では、AI駆動開発により大きく変化してきた2025年版の最新ポイントを含めて、失敗しない開発会社の選び方を解説してきました。開発実績や得意分野の確認、会社の規模・体制・安定性、担当者のコミュニケーション力、提案内容、アフターサポート、そして費用面の比較検討まで、総合的に判断することが重要です。さらに発注前の準備を十分行い、契約後も適切に関与して進めることで、システム開発プロジェクトの成功確率は飛躍的に高まります。 2025年現在、AIやクラウドをはじめ技術トレンドは日進月歩で変化していますが、本質は変わらず、「信頼できるパートナー」と二人三脚で進める開発こそが成功への近道です。本記事の内容を参考に、自社にぴったりのシステム開発会社を見極めてください。適切な会社選びと準備をもってプロジェクトに臨めば、きっと「この会社に頼んで良かった!」と思えるシステム開発が実現できるはずです。


